
【保存版】シリーズは、筆者であるツベルクリンが色々なジャンルの有益かつ無益な情報を書いていくシリーズ記事です。今回は「好法師のエッセイ『徒然草』が教えてくれる生き方のヒント」がテーマです。
中学校に上がると国語で古文を習います。その古文の授業でほぼ100%習う作品が鎌倉時代後期に兼好法師が書いた(とされる)随筆『徒然草(つれづれぐさ)』です。随筆とは今で言うエッセイのような文章とお考えください。
ほぼ100%の日本人が一度は学んだことある文章とかヤバくないですか。しかも、現在では電子書籍化されてるんですよ。超ロングセラーじゃないですか。けれども、古文が難しすぎて肝心の『徒然草』の内容が全然頭に入ってこない生徒もたくさんいたはずです。
『徒然草』は全244段から成る結構長編なエッセイです。エッセイなので、兼好法師が普段の生活を通して考えたことを書き残しています。文章自体は鎌倉時代に書かれたものですが、よくよく読んでみると現代社会でも通用する思想なり考え方を私たちに教えてくれています。もっと言えば、『徒然草』は人間としての生き方を教えてくれる作品なのです。
今回は、『徒然草』の中からいくつかピックアップし、兼好法師の考え方をご紹介していきます。その中に、現代に生きる私たちが考えるべき先人の教えが含まれているかもしれません。

『やがてかけこもらましかば、口をしからまし』(32段目)
現代語訳:お客を送り出してすぐに戸締りをしてさっさと家の中に入ってしまったらどんなに味気ないだろう
兼好法師は知人と一緒に、知人の知り合いの女性の家を訪れました。やがて、帰る時間になって女性の家を後にした際に、彼女は2人が家を出た後もしばらく戸を開けたままにしていたのです。それに気づいた兼好法師が感心して上記の文書を綴ったのです。
とある観光地の人力車屋さんでは、お客様を案内してお別れした後も、すぐに立ち去るのではなく、そのお客の姿が見えなくなるまでずっと立ったまま見送りをしているそうです。別れ際の余韻を上手く演出しているのです。
現代社会においても、宅配便の方が配達してくれた後、ぶっきらぼうにドアをバタンと閉めてしまうのは、あまり気持ちのいいものではないかもしれません(防犯上の問題はあるかもしれませんが…)。
扉の閉め方1つとっても、その人の人となりが出てしまうのです。そして、このような心遣いは『朝夕の心づかひによるべし(日ごろの心遣いから自然に出るものだ)』と兼好法師は考えているのです。心遣いは急に出せるものではないのです。

『少しのことにも、先達はあらまほしきなり』(52段目)
現代語訳:些細なことでも教えてくれる人がいたほうがいい
表面的な意味だけならば『教えてくれる人がいた方が物事はスムーズに運ぶよなぁ~』ってことになりますが、兼好法師の言いたいことはそれだけではありません。大事なのは『"教えてくれる人がいたほうがいい"と気づけるか?』ということです。
そのように気づけるためにはまず『自分が知らないことを知る』ことが必要です。無知を自覚して初めて、先生の必要性を知るのです。自分が出来ると思いこむ、知らないことは何もないと傲慢な態度を取っていると、大きなミスを招きかねないのです。

『よくわきまへたる道には、必ず口重く、問はぬ限りは言はぬこそ、いみじけれ』(72段目)
現代語訳:よく精通していることについては、口数を少なくして、聞かれない限りは黙っているのが立派な態度である。
ことわざで言う「能ある鷹は爪を隠す」ってことです。知っていることを聞かれても無いのにあれこれ喋りまくるのはみっともない、と言いたげです。ましてや、知ったかぶりで話すのはなおさら恥ずかしいことだ、と考えているのです。
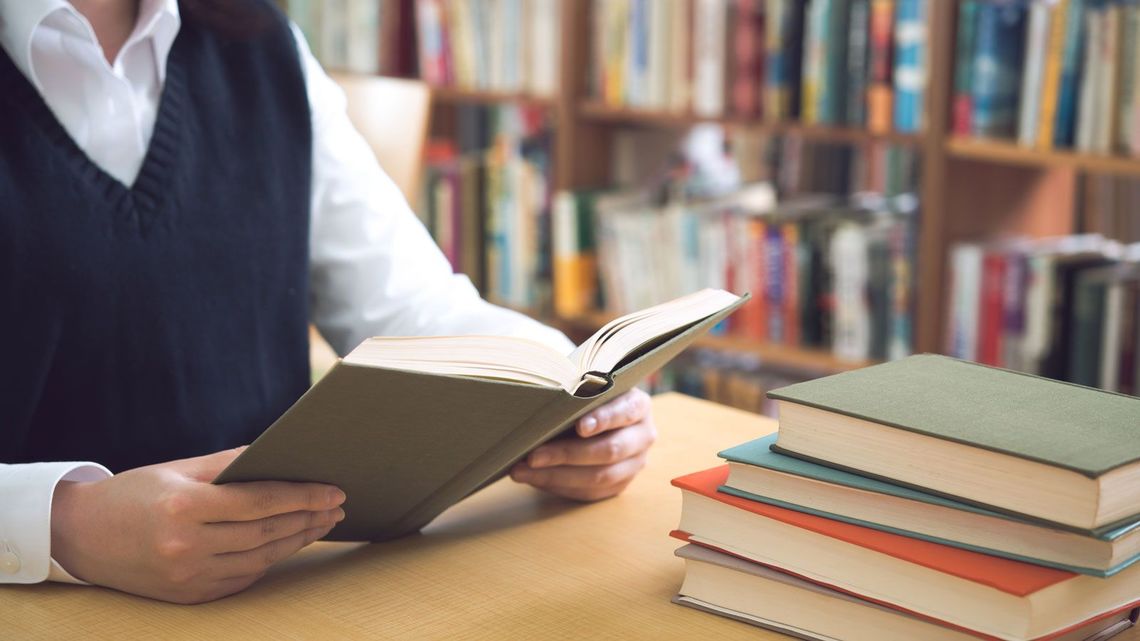
『ただひとりあるのみこそよけれ』(75段目)
現代語訳:1人でいるのが何よりも好ましいことである。
兼好法師はこの台詞の後に、『周囲の人々に合わせていると、心が安定することが無い。周囲に合わせてせわしく動き回っていると、本心を失って自分のやることを忘れてしまう』と説いています。兼好法師は、1人の時間を持つ事で心の安定を取り戻せると考えているのです。
ブログやtwitterで他の人と絡むのも有意義なものではありますが、その時間と同じくらいに1人で何かに没頭する時間も必要だと思うのです。1人の時間で自分に向き合い、自分を高めていくことが、現代人には必要なことなのではないでしょうか?

『初心の人、二つの矢を持つ事なかれ。後の矢を頼みて、初めの矢に等閑(なおざり)の心あり。毎度、ただ得失なく、この一矢に定むべしと思へ』(92段目)
現代語訳:初心者が2本の矢を持ってはいけない。2本目があるからと油断し、1本目の矢をなおざりにしてしまう。毎回毎回、この一本の矢で決めようと思いなさい
この文書は、中学校の国語の試験問題によく出てくるので見たことがある人もいるかもしてません。弓道に関する話です。
弟子が2本の矢を持って的に向かって立ったのを見た師匠が弟子に対して注意を促した場面です。油断している時は自分では気が付かないものです。それを見抜いた師匠は、『この一矢に定べしと思へ』と指摘したのです。『まだ2本目がある』と思っていてはいけないという教えです。

『勝たんと打つべからず。負けじと打つべきなり』(110段目)
現代語訳:勝とうとして打ってはダメだ。負けないように打つべきだ
ここでは賭け事のことを例えに出して言っていますが、その後兼好法師は『道を知れる教え、身を治め、国を保たん道も、またしかりなり』と、自分の身を立て、さらには国を治める際にも同じだと言っています。
勝つ方法ばかり考えていると、自分の弱点を見つめることがおろそかになってしまいます。勝ち続けている時は調子よくても、一度負けてしまうとそこから坂道を転がるように失速してしまうかもしれません。自分の弱点をつぶしていく事が負けない=勝ちにつながると言っているのです。

『能をつかんとする人、「よくせざらんほどは、なまじひに人に知られじ。うちうちよく習ひ得て、さし出でたらんこそ、いと心にくからめ」と常に言ふめれど、かく言ふ人、一芸も習ひ得ることなし』(150段目)
現代語訳:芸を身に着けようとする人は「上手になるまでは人前に出ずにこっそり練習し、上手になってから人に見せたほうが良いだろう」と言うけど、そういう人はいつまでたっても上手にならない
日本人は人前で恥をかくことを良しとしません。『陰で練習して上手くなってから人前に出よう』と考えます。ところが兼好法師は、人前で恥をかかない限り上達はしない、と断言しているのです。ブログだってそうです。書いて人に読んでもらわない限りは、文章力は上達しないものです。

『必ず果し遂げんと思はん事は、機嫌を言ふべからず。』(155段目)
現代語訳:必ず成し遂げたいと思ったことは、タイミングをどうこう言わずにやりなさい。
ここで言う「機嫌(きげん)」とは、気分のことではなく、時期のことを意味します(もともとは仏教用語です)。この文章の後に『とかくのもよひなく、足を踏み止むまじきなり(あれこれ準備したり足を踏みとどまっていてはいけない)』と書いています。いつやるの?今でしょ!精神です。

『道を知らざらん人、かばかり恐れなんや』(185段目)
現代語訳:その分野をよく知らない人がこれほどまで恐れるだろうか(いや、恐れないだろう)
現代語訳だけではいまいちピンとこないので、その前段階の話を紹介します。ある有名な馬乗りに会った兼好法師。その名人は、今から乗ろうとする馬の様子を見て『あの馬は気が立っているから乗ると危ない。乗るべきではない。』と乗馬をあきらめたのです。
その態度を見た兼好法師は感動し、『その道の達人でなかったら何も考えずに乗ってしまい、大けがをしたであろう』と考えたのです。その道の達人であればあるほど、少しの変化を気づき、常に恐れる気持ちを持っているから失敗しない、という教えです。
言い換えると、『失敗するかもしれない』という緊張感を常に持ち続けている人は、慎重に行動が出来るし、失敗しないように努力出来ると諭しているのです。
終わりに…
このように真面目で訓示的な文章を残している兼好法師ですが、時折そのクソみたいな性格をのぞかせています。
例えば、『徒然草』の中で"友人にすべき人"の例として「物をくれる人」と断言しています。そういう人間臭いところも兼好法師の魅力の1つなのです。
当ブログのtwitterアカウントはこちら
ツベルクリン@アウトローブロガー (@tuberculin0706) | Twitter
